自社に最適で信頼できるホームページ制作会社の選び方
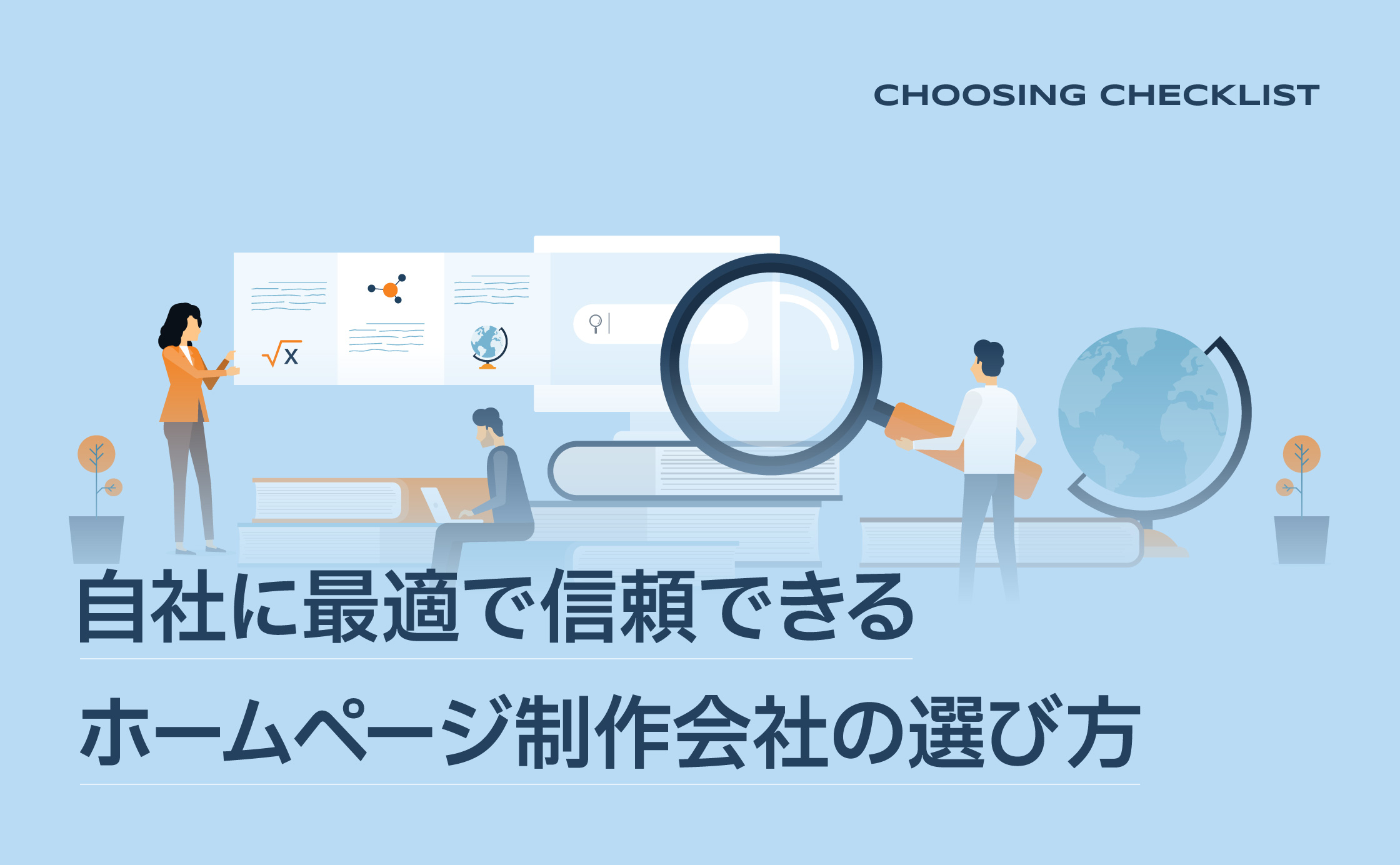
自社のホームページ制作・リニューアルを依頼する際、どの制作会社に依頼すればよいか悩む企業は多いのではないでしょうか?
ホームページは自社と顧客、または求職者といった重要な関係先と多くの接点を持ち、コミュニケーション機会を創るためのマーケティングツールです。自社に適した信頼できるホームページ制作会社を選ぶことは、ビジネスの発展に効果的なサイトを構築し、会社の成長につなげることができます。
本記事では「制作会社」の視点で、制作会社を選ぶためのポイントを解説します。
事前にある程度決めておくべきポイント
まずは自社が何のためにホームページを必要とするのか、適した提案を受けるために検討しておきたい基本事項です。
ホームページに期待する成果(発注目的)を明確に
ホームページは「名刺代わり」ではなく、自社が抱える課題解決を体現するための強力なツールです。このため、ホームページに期待する成果を明確にしておく必要があり、まずは自社の抱える課題を洗い出しておくことが大切です。
期待する成果を曖昧にしてしまうと、望む結果に至らず無駄なコストが発生したり、自社にとって大きなデメリットを生む可能性が高まります。
場合によりますが、必ずしも制作会社がヒアリングですべて掴みきれるわけではない点は理解しておかなければなりません。
そこで、この期待する成果を制作会社とスムーズに共有し、必要な機能やデザインのアプローチを提案に反映するため、以下を参考に検討しておくと安心です。
もし期待する成果を明確にできない場合は、まずはそこから模索したいと制作会社に伝えておきましょう。
- 自社(または商品・サービス)の認知度を高めたい
- 採用活動を強化したい
- 課題に応える姿勢などビジネス上の信頼感を得たい
- 複雑な情報を適切な設計で提供したい
希望予算・納期を決める
ホームページの制作費用は、規模や機能・デザインに求める品質によって大きく異なります。また、同じ条件でも制作会社によっても大きな開きがあります。事前に予算の上限や希望納期を設定し、無理のない範囲で計画を立てることで、自社にとって最適な制作会社を選定する基準になると同時に、制作会社も具体的な提案をしやすくなります。
おおよその予算・納期の設定がない場合は、制作会社も最大限パフォーマンスの高い提案をしますので、そのまま費用・納期も大きく長くなります。最大限のパフォーマンスを一番求める場合を除き、自社の条件に適した提案を受けるため、事前に無理のない範囲での予算・納期設定をしておくことが無難です。
提案依頼書(RFP)など資料作成は必要?
複数の制作会社に提案を依頼する「相見積もり」の場合、提案依頼書(RFP)を作成すると同じ基準で選定しやすくなります。提案依頼書(RFP)には以下を参考に書き出せる範囲で記載するとわかりやすいです。
提案依頼書(RFP)を用意できない場合でも、基本的には制作会社がヒアリングで要件を引き出してくれます。ただし、制作会社によってヒアリングのベクトルは違うので、自社の要望とずれがないか適切な確認が必要です。
- プロジェクトの目的
- ターゲット像
- 自社の課題
- 必要とする機能/コンテンツ要件
- デザインの方向性
- 概算予算/納期
- 運用/保守の要件
- 提出してほしい資料/情報
- 選定基準/条件/スケジュール
制作会社の「候補先選定」段階で確認しておくべきポイント
Google検索などで制作会社を探し、候補先を選定する段階で確認しておくべきポイント・注意点です。
自社の理想と類似する実績があるか
制作会社は基本的に「制作実績」をホームページに掲載しており、その実績から制作会社の技術力を推し量ることができます。また、類似する実績があればそこを起点にすり合わせができるため、スムーズに進められる可能性が高まります。
デザインや機能の品質にこだわる場合、実績間で同じようなデザインが連続していないかといった点は強く確認しておくべきポイントです。特に、安価であるのに「オリジナルで制作」としている制作会社も、場合によってはテンプレートやフォーマットでの制作をしている可能性もあるため、前述の「期待する成果」を意識する場合は安さだけで判断しないようにすることが大切です。
制作会社の特長が自社と合っているか
制作会社はそれぞれ必ず特長があり、自社の求めるものに合っているか確認しておくことは最も大切なポイントの一つです。例えば、商品・サービスを効果的に訴求したい場合は「デザイン・ブランディング型」、より上流である集客の伴走・支援を求める場合は「マーケティング型」といったように、制作会社が持つ知恵・ノウハウを最大限自社に活かせる特長から選定することは重要です。
この特長は、制作会社の制作実績、またはサービスページからある程度判別することが可能です。
- 表現を大切にする「デザイン・ブランディング型」
- 機能を大切にする「システム型」
- 集客を大切にする「マーケティング型」
- 安価を大切にする「ローコスト型」
納品後のサポート体制がどの程度あるか
ホームページは公開後も適切なメンテナンスが必要です。更新作業やトラブル対応のサポートがあるか、費用はどのくらいかかるのかを確認しておくと安心です。特に、WordPressなどCMSを利用する場合、適切なアップデートはサイト保守・運用の観点から重要なポイントになります。また、運用に限らず納品直後のトラブルに対しどれくらいの期間まで保障があるか、保障外のトラブルはあるかといった点も確認は必要です。
なお、制作会社のホームページで保守・運用の紹介がない場合も多く、この場合は商談のできるだけ早い段階で確認しておきましょう。
制作会社の対応エリアと距離感
対面での打ち合わせを希望する場合、制作会社の所在地も重要なポイントです。遠方の会社に依頼すると、打ち合わせの回数や移動コストが課題になる可能性があります。一方、オンラインミーティングが主流の現在では、距離にこだわらず実績や対応力で選ぶことも選択肢の一つです。
ただし、初めてのホームページ制作や高い品質を重要視する場合、オンラインではなく対面で打ち合わせできる方が細かいすり合わせがしやすく安心できます。まずは対面できるエリアで制作会社の候補を探し、見合った会社がなければエリアを広げていくことがよいかもしれません。
制作会社の「発注先選定」段階で確認しておくべきポイント
商談後、実際にどの制作会社に発注するか、その選定段階で確認しておくべきポイント・注意点です。
自社の目的・課題を深く理解する姿勢・ヒアリングがあったか
信頼できる制作会社はヒアリングを丁寧に行い、自社の目的や課題をしっかりと理解してから提案に繋げます。形式的なやり取りだけでなく、自社の強みやターゲット像まで深掘りする姿勢があるかをチェックしましょう。
避けたいのは、どのようなページが必要か、どのような配色にするか、制作会社に比べ当然経験の少ない顧客に「答え」を聞くことに終始する場合です。自社の課題解決ではなく、ホームページを機械的に作ることだけにフォーカスしている可能性が高く、効果的なホームページに至らないことがあるからです。
デザインとしてのトンマナも大切ですが、自社と同じ視点で課題を見つめるスタンスがあるか、ヒアリングから感じとることが大切です。
見積書に不安が残っていないか
提案された制作費用の内訳や料金体系は納得できるものか、不明瞭なものがないか適切に確認し、「不安」が限りなく少ない状態で選定しなければなりません。不安に対し、制作会社から気づいて先回りの配慮があれば大きく信頼できます。
しかし、アバウトな設計や見積もりなど不安が大きい場合、見切るのではなく、改めて説明の機会を求める方が適切です。基本的には新たな検討材料などを制作会社が用意し、不安解消に努めてくれますが、いくら提案が良くても契約を急ぐなど不安を大きくさせる場合は候補選定から見直すことも大切です。
また、見積書には専門的な用語が多く、理解の行き違いがないかも大切な確認事項です。特に、追加費用が発生しないか、運用費が高額になりすぎないか、契約期間があまりにも長すぎないかといった点は重点的に担当者へ確認しておきましょう。
【最重要】自社に見合った実績と同じデザイナーが担当してくれるか
自社の求めるデザイン・機能面の品質に近しい実績があった場合、実際にそのデザインを手掛けたWebデザイナーが担当してくれるか確認しておきましょう。会社によっては外部のデザイナーに委託する場合もあるため、期待する品質が得られるかを事前に把握しておくことは大切です。
また、ディレクターや営業担当だけでなく、実際にデザインを手掛けるWebデザイナーと直接話せるかといった点も重要なチェックポイントです。細かなデザインの意図やニュアンスを共有しやすくなるため、より自社に効果的なホームページ制作につながります。
オーダーメイドでホームページ制作を依頼する場合、コミュニケーションは最も重要です。お互いの意見を尊重し合い、同じ視点で目的を見つめられるか、ぜひ、本記事を参考に、納得のいくパートナーを見つけてください。
弊社が大切にしていること
弊社は「ビジネス課題に即した戦略的なクリエイティブ提供」を使命として、単なるWeb制作ではなくマーケティング・ブランディングを組み込んだ設計提案を強みとしています。
お客様の潜在的な課題発見からその解決に至る施策を、必要に応じて上流から支援いたします。
また、提案依頼書(RFP)をお客様といっしょに見立てていく取り組みもしており、制作会社の候補選定におけるご負担軽減につとめています。
神戸を中心に、全国でホームページ制作・ブランディング支援をご検討の企業さまからのお問い合わせ・ご相談お待ちしております。


