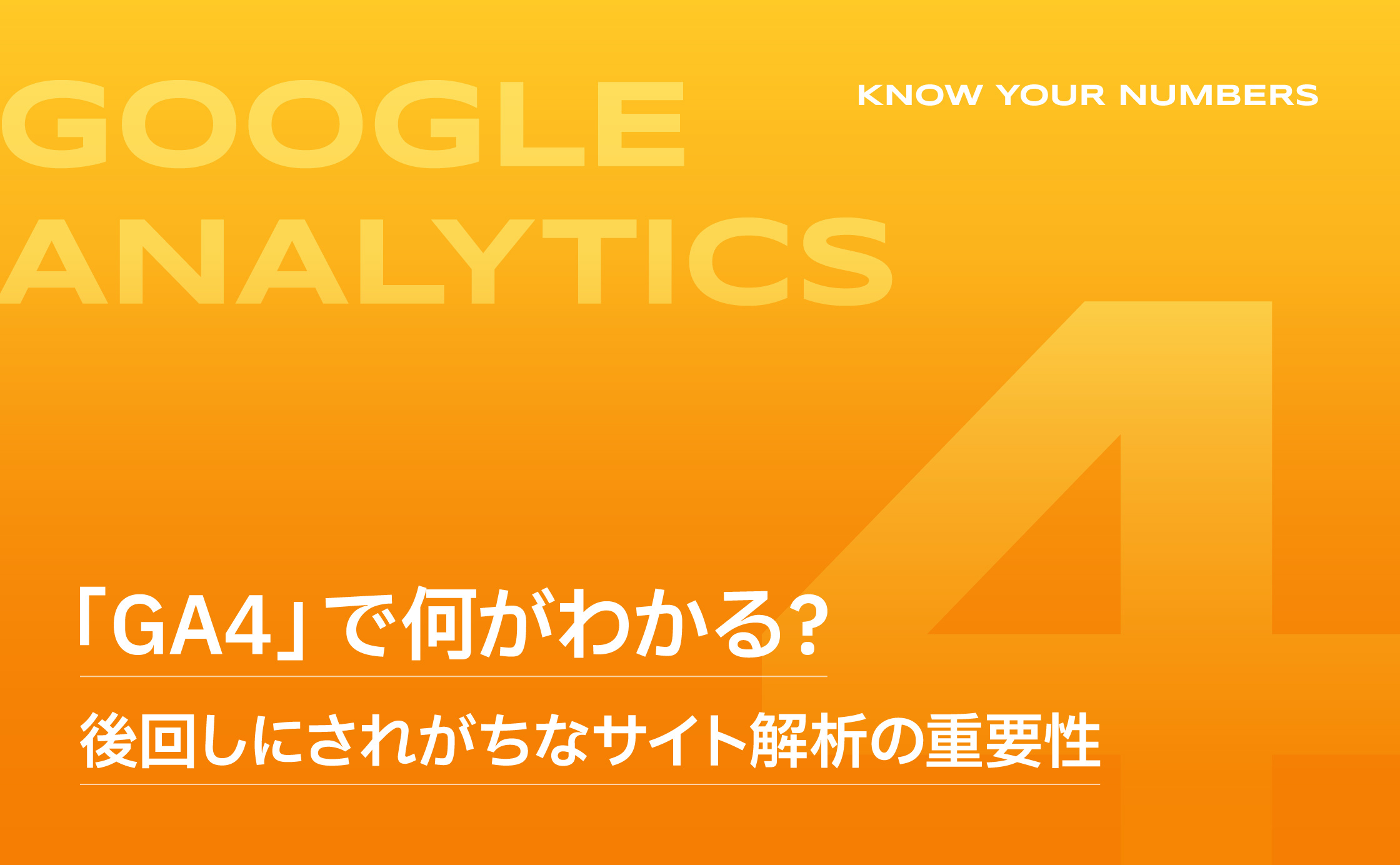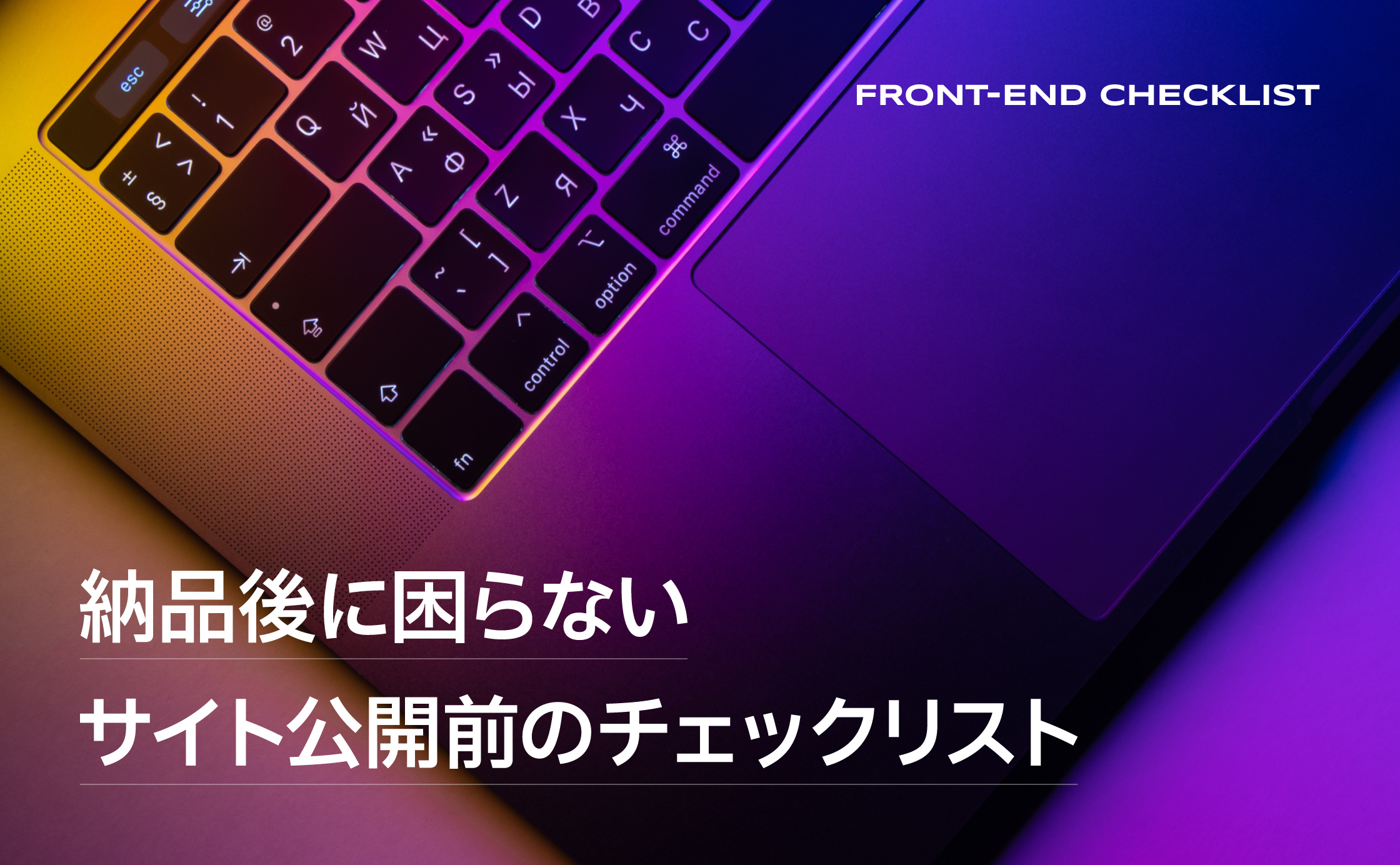古さを価値に変える、ホームページリニューアルの新しい考え方

ホームページを古いまま放置すると、集客や集患、採用で不利になるだけでなく、ブランディングや認知にも悪影響が及びます。「この会社は変化に対応できていないのでは?」と見られてしまうリスクもあるのです。
一方で、古い中にも効果的な要素は必ず存在します。そうした価値ある要素を残しつつ、すべてを「刷新する」から「発展させる」へと比重を移すことで、従来の単純なリニューアルとは異なる、新しい視点からの最適解を導き出すことができます。
よくある悩み・課題
ホームページのリニューアルを検討する企業が最初に感じるのは、現状に対する不満や不安です。こうした課題は放置すると、企業の印象やブランド価値そのものを下げてしまいます。以下は代表的なよくある課題を大きく4つのカテゴリーに整理したものです。
デザイン・見た目の問題
- ホームページ全体のデザインが古く、第一印象で「時代遅れの会社」と思われてしまう
- 色やフォント、レイアウトが統一されておらず、ブランドイメージが伝わらない
- 他社サイトと比較されたときに、洗練度や信頼感で劣ってしまう
ユーザー体験(UX)の問題
- ナビゲーションが複雑で、欲しい情報にたどり着きにくい
- スマホやタブレットでの表示が最適化されておらず、閲覧や操作が不便
- ページ読み込み速度が遅く、途中で離脱されやすい
- 問い合わせや採用フォームの入力が煩雑で機会を逃している
情報の鮮度・信頼性の問題
- 新しい実績や商品情報を載せたいが、どうすればよいか分からない
- 採用ページが古いままで、若い人からの応募がほとんど来ない
- 展示会や商談で関心を持ってもらっても、サイトを見た瞬間に熱が冷めてしまう
運用・体制の問題
- 社内に詳しい人がいないため、更新が止まってしまっている
- 担当者が退職してしまい、誰も運用方法が分からず更新できなくなった
- 更新作業が属人化しており、引き継ぎできないまま放置されている
古さを強みに変える視点
古いホームページやWebサイトをそのままにすると「時代遅れ」と見られがちですが、長年使われてきた要素はブランドの象徴にもなります。残す部分と更新する部分を見極めれば、単なる古さではなく、ブランド戦略やユーザー体験に直結する価値として活かすことができます。


視覚的DNAの一貫性
過去の広告・看板・印刷物などから受け継がれている色やタイポグラフィを分析し、コーポレートアイデンティティの一部として再定義。単なる「残す」ではなく「意図を持って現代に翻訳」する。
歴史をストーリー化する資料資産
古い写真や新聞記事、パンフレットを単に「沿革」に載せるだけでなく、ブランドストーリーの章立てやSNS発信のコンテンツとして再利用。過去資料を「生きたマーケティング資源」へ昇華。
ユーザーに継続して刷り込まれた習慣や認知
「看板の色を見るとこの会社を思い出す」「昔からのキャッチコピーが親しみを持たれている」など、無意識下に蓄積された認知資産。これを断絶せず、新デザインに意図的に橋渡しする。
空間や人材に宿るブランド感
古い工場・店舗の佇まいや、長年勤める社員の言葉。物理的な「古さ」をビジュアルやインタビュー記事として残し、信頼感とストーリーの裏打ちにする。
プロセスとしての古さ
長年続く製造方法・仕事の流儀・地域との関わり方を「古いもの」としてではなく「受け継がれる技術・文化」として再定義。単なるノスタルジーではなく「強み」として可視化。
実務的なリニューアルのポイント
実際にホームページをリニューアルする際には、デザイン変更だけでは不十分です。情報設計やSEO対策、運用フローまで具体的に改善してこそ、成果につながり、ブランドイメージを守る・発展させるリニューアルになります。さらに、前章で触れた「古さの価値」をどう実務に落とし込むかが重要です。残すべき要素を活かしながら刷新部分と統合することで、より説得力のあるサイトに仕上がります。
デザイン刷新だけでなく「情報設計」をやり直す
- メニュー構成を整理し、「誰が見ても欲しい情報にすぐ届く」状態を作る
- サービスや事業内容を分類し直し、ユーザーの課題解決に直結する流れにする
- 過去のキャッチコピーや広告要素を現代的に翻訳し、メニューやタイトルに反映する
スマホ最適化は“見る”だけでなく“操作する”観点で
- ボタンのサイズ、フォーム入力のしやすさまで配慮する
- 特に採用エントリーや問い合わせ導線は、スマホ中心で設計
- 古いデザインパターンを捨てるのではなく、印象的な配色や余白感を現代のUIに融合する
SEOを「守る+強化する」設計
- 既存ページの検索評価を落とさないよう、リダイレクトやURL設計を丁寧に行う
- 狙いたいキーワードを改めて整理し、記事や事例紹介ページを追加する
- 過去の記事や資料をSEO資産として再編集し、ストーリー性を持たせて発信する
更新フローを担当者基準で考える
- WordPressなどCMSを用い、写真やテキストを誰でも簡単に入れ替えできるようにする
- 更新マニュアルを図解付きで準備し、社内引き継ぎが容易になるようにする
- 長年の運用ルールを棚卸しし、使えるものは残して新しいフローに統合する
会社の歴史や強みをストーリーに変える
- 古い施工写真や創業当時の資料を「沿革ページ」だけでなく、TOPやサービスページにも散りばめる
- 「古さ=蓄積された経験」と見せるコンテンツ編集を行う
- 古いパンフレットや社員インタビューを再編集し、ブランドの軸を補強する
採用視点を組み込む
- 働く人の声」「社内風景」「1日の流れ」などを入れ込み、求職者が安心して応募できる情報を追加
- 古さを「安定感」に変えつつ、若手が共感できるビジュアルやコピーを組み合わせる
- 創業から続く価値観や文化を言語化し、採用メッセージに反映する
担当者にとってのメリット
リニューアルを通じて運用面を実務的に改善すれば、担当者の負担を減らしつつ「更新できない会社」というマイナスの印象をなくして、ブランドの信頼性も守ることができます。
営業担当にとっては
新しい情報(実績や商品など)をすぐに掲載でき、商談で最新情報を提示できるようになります。
採用担当にとっては
求人の有無を簡単に更新でき、応募者に正確でタイムリーな情報を伝えられるようになります。
総務担当にとっては
イベントやお知らせを短時間で反映でき、情報発信のスピードと正確性が向上します。こうした仕組みが整えば、社内の「誰も更新できないから情報が古いまま」という課題は解消されます。結果的に、担当者の心理的負担も軽くなり、サイトが生きた情報発信ツールへと変わります。
従来リニューアルでは得られない効果
古さを戦略的に活かしたリニューアルは、集客・採用・ブランド戦略の柱を中心に、実務面でも多角的な成果をもたらします。逆に、表面的な刷新にとどまると「せっかくの歴史や信頼を失う」というリスクもあるため、戦略性が欠かせません。
集客の面では
古い広告や施工写真を活かして実績や歴史を訴求しつつ、情報設計やSEO、デバイス間の最適化を行うことで、新規顧客の流入を増やせます。従来型の見た目刷新だけでは得られなかった「信頼に裏打ちされた集客効果」が期待できます。
採用・社内エンゲージメントの面では
古い社屋写真や創業時のメッセージを残すことで安定感を示し、同時に最新の社員インタビューや働く環境を組み合わせることで若手にも親近感を与えられます。さらに、企業の歴史や伝統を再編集して社内で共有することで、社員が誇りや共感を持ちやすくなり、定着率やモチベーション向上にも寄与します。
ブランド戦略の面では
過去のパンフレットや広告資産をブランドストーリーとして再編集し、「変わらない価値」と「進化する姿」を両立させます。SNSや広報活動にも活用でき、他社との差別化や長期的なブランド強化につながります。
地域に根ざす優位性の面では
古い取り組みや地域との関わりを整理・発信することで、地元企業としての信頼を強調できます。単なる地域密着の表現ではなく、「歴史とともに歩んできた証」を示すことで、CSRや地域ブランドとしての価値を訴求し、競合にはない優位性を築くことができます。
私たちができること
株式会社Knotusではホームページのリニューアルに伴い、より効果的に期待する成果へつなげるためのパンフレットや会社案内などのグラフィックデザインも合わせて提案可能です。また、ブランドコンセプトの再定義や開発段階から参画することもでき、単なるリニューアルにとどまらない包括的な支援をご提供いたします。
ご相談やお問い合わせはお気軽にお声がけください。神戸をはじめとした地域企業の皆さまに最適なリニューアルの形を共に考えさせていただきます。
まとめ
ホームページを古いままにしておくと「停滞した印象」を与え、ブランド価値を損ないます。だからこそ、古さを活かして磨き直すリニューアルが必要です。
古さをすべて消すのではなく、受け継ぎながら戦略的に磨き直すことがリニューアル成功のカギです。残すべき価値と刷新すべき要素を見極め、実務的な運用改善とブランド戦略を両立させることで、サイトは単なる会社紹介から「営業と採用を支える実務的な武器」へと進化します。これは、投資以上のリターンを生む取り組みとなるはずです。
関連記事
- デザイン
2025年4月30日
「GA4」で何がわかる?後回しにされがちなサイト解析の重要性
- デザイン
2025年2月17日
納品後に困らない、サイト公開前のチェックリスト